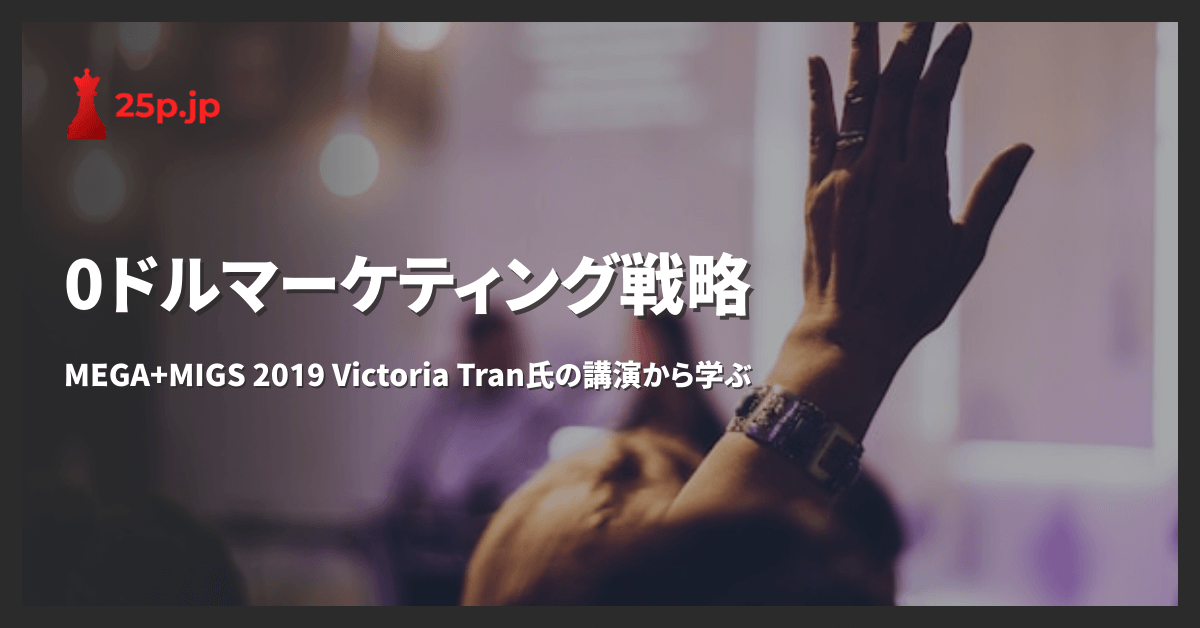この記事では、MEGA+MIGS 2019で当時Kitfox Gamesのコミュニケーションディレクターを務めていたVictoria Tran氏による講演「The 0 $ marketing game plan」をもとに、インディーゲーム開発者に役立つマーケティング戦略と考え方を整理しました。
はじめに
「0ドルマーケティング」と聞くと、SNSだけで話題を作る、あるいはバズを狙うといったイメージがあるかもしれません。しかしVictoria氏は冒頭で、その考えに対して明確な否定を示しています。
この講演タイトル、実はちょっと嘘です。完全な0ドルマーケティングなんて存在しないんです。
では、予算が限られている中で、どのようにして注目を集める存在になれるのでしょうか。そのための具体的な実践例と考え方が、講演では丁寧に共有されていました。
フックの作り方 ─「説明なしでも面白そう」か?
フックとは、最初の一文でユーザーの興味を引く仕掛けのこと。Victoria氏は、説明文からゲーム名や固有名詞を取り除いたうえで「他のゲーム名に置き換えても成立するなら、そのフックは弱い」と明言しています。
実際に、「高速2Dアクションアドベンチャー。美しいアートと重厚な物語」という説明文が、Boyfriend DungeonにもHollow KnightにもDead Cellsにも当てはまってしまう例を提示し、開発者に「より具体的かつ感情に刺さるフレーズ」を模索するよう呼びかけていました。
私もこれは強く共感した部分で、日々SNS投稿をする中でも、ゲームタイトルを知らない人がスクロール中に“立ち止まる一言”を作る難しさを痛感しています。
Victoria氏によるアドバイス:
- 「Metroidvania」「roguelike」などの定型語を排除してみる
- 感情を喚起するキャッチコピーを意識する(例:「恋人が武器になるダンジョンRPG」)
- 一般ユーザーでも直感的に内容をイメージできるかをテストする
Steamストアページと「カプセル画像」の工夫
ここで言う「カプセル画像」とは、Steamストアでゲームが一覧表示された際に出るアイキャッチ画像のことを指します。この画像の「クリック率(CTR)」は、ユーザーがゲームに興味を持つ最初の入口となるため、非常に重要です。
Victoria氏は、Boyfriend Dungeonで行ったカプセル画像の改善事例を紹介しており、初期はタイトルロゴ+恋愛要素を前面に出したビジュアルだったものの、CTRが伸び悩んだため、戦闘シーンに変更。しかしその画像が暗くて背景に埋もれがちだったため、最終的に明るい人物写真に切り替えたところ、CTRが2%を超えたとのことです。
この話を聞いて、私も今後クライアント向けのバナー制作などで、画像がサムネイルとして並んだときにどう見えるかを、より意識していこうと感じました。
Victoria氏によるアドバイス:
- ストアページでは最初に表示されるスクリーンショットの質が勝負
- カプセル画像は「Steamの背景に埋もれない明るさ・構図」が大切
- CTRの目安は2%以上。下回る場合は画像を再検討すべき
プレスへのアプローチは「件名」がすべて
Victoria氏は、プレス向けのメール配信で最も重要なのは「件名」だと語ります。なぜなら、受信箱には毎日数十通以上のメールが届き、まず“開かれるかどうか”が最大の関門だからです。
講演では、実際のゲームジャーナリストの受信トレイのスクリーンショットも紹介されており、いかにメールが埋もれやすいかが視覚的にも伝わってきました。
特に印象に残ったのは、次のような発言です:
どんなに素晴らしい内容のメールでも、件名で興味を持たれなければ誰にも読まれない
そして、「Lewd buttdates」という大胆な件名が、実際に多くの反応を得たというエピソードも紹介され、タイトルでの“勝負”の重要性が強調されていました。
Victoria氏によるアドバイス:
- メールの件名でニュース性やユーモアを伝える
- ジャーナリストの過去記事や好みに合わせて、一言を添えると効果的
- 全大文字・過剰な感嘆符はスパムフィルターにかかるリスクがあるため避ける
インフルエンサーとの関係構築は「中堅層」が鍵
Kitfoxでは、大物インフルエンサーよりも「中堅で視聴者との距離が近い配信者」との関係構築を重視しています。
Victoria氏は、自社のゲームがストーリー重視でネタバレ要素も多いため「配信にはあまり向かない」という前提がありながらも、それでも可能な範囲で交流を図ってきたと語っています。
印象的だったのは、「ゲームキーを渡すだけでも喜んでもらえる」という言葉と、「配信を見に行ってリアクションを送ることで関係性が深まる」という実際のエピソードでした。
私、SNS運用やコミュニティ対応をしている中で、こうした“一対一の丁寧なやり取り”が結果的に最も信頼される手段であることを感じているため、この姿勢は強く共感します。
Victoria氏によるアドバイス:
- 視聴者参加型の要素(チャット名をゲーム内キャラに使うなど)が効果的
- 配信者とはフレンドリーかつ丁寧な関係を築くことが重要
- インフルエンサー戦略は規模よりも関係性の深さを優先する
SNS活用は「信頼構築と接触回数の最大化」が目的
Victoria氏は、「SNS=無料で効果的な販売手段」というイメージに対しても現実的な視点を提示しています。SNSは直接的なコンバージョン(購入)にはつながりにくく、それだけに依存すべきではないと述べています。
その一方で、SNSには明確な役割があり、特に「単純接触効果(mere-exposure effect)」──何度も見かけることで安心感や興味が生まれる心理的効果──を生かすべきだと強調していました。
実際のデータでは、TwitterからのSteamストアへの流入は比較的高いコンバージョン率(2〜5%)を示す一方で、Facebookからの流入は極めて低かったとのこと。これをもとに、Victoria氏はTwitterを主戦場に据えたと説明していました。
私も複数のSNSアカウントを運用してきた経験から、「リーチより関係構築」を目的とした運用が結果的に成果につながる場面を多く見てきました。SNSの数字だけで評価せず、その背景にある接触と信頼を重視すべきだと改めて感じました。
Victoria氏によるアドバイス:
- SNSごとに成果を計測し、集中するチャネルを見極める(例:Twitterに注力)
- 投稿にリンクを入れる際は1〜2個までに絞る(多すぎると逆効果)
- ハッシュタグ(#gamedevなど)は開発者向けであり、一般ユーザーには届きにくい
Discord活性化には「参加したくなる理由づくり」が鍵
Victoria氏は、Discord運営について「Botの導入やゲーム的な仕組みよりも、“開発者と話せる”こと自体が最大の価値」だと語っていました。
特にリリース前で話題にしづらい時期でも、「一足先に情報を見られる」「開発中の素材にコメントできる」といった特典的な体験を用意することで、ファンとの関係を深めているそうです。
印象的だったのは、「ツイート前の画像を先にDiscordで公開して、キャプション案を募集する」という実践例。参加する価値や意味を丁寧に作り出す姿勢に共感しました。
Victoria氏によるアドバイス:
- Discordでは「先行公開」「参加型投稿」など“特別感”を演出する
- Botやランク機能に頼りすぎず、開発者の発信と会話を大切にする
- 本当に興味を持っている少人数との濃い関係が、後の広がりにつながる
まとめ ─ マーケティングの本質は「人との関係」
ここまで紹介してきたVictoria氏の講演を通じて改めて強く感じたのは、どの施策も「人と人とのつながり」を軸にしているということです。
- フックで心を動かし、
- ストアページで“面白そう”を確信に変え、
- SNSやDiscord、メールなどで“継続的な信頼”を育てていく。
個人的に特に響いたのは、SNSもインフルエンサー対応も、すべて「大勢に向けた一発勝負」ではなく、「一人ひとりとの丁寧な対話」の延長線にある、という考え方です。
私はこれまでSNS運用の現場で、数値的な成果やエンゲージメントの数ばかりに目を向けてしまい、「本当に意味のある関係が築けているのか?」という視点を後回しにしてしまうことがありました。
どうしても即効性や目に見える“結果”を求めがちになる中で、Victoria氏の「関係性こそがマーケティングの基盤になる」という考え方には、なるほどと思わされました。これまでの運用を振り返ってみても、たとえ数字に現れにくくても、コミュニティ内でじわじわと共感や信頼が育っていくような瞬間こそが、実は最も価値のあるものなのかもしれないと、改めて感じています。
インディーだからこそ、遊び心と人間らしさを大切にできる
この言葉のとおり、予算がないからこそできるマーケティングの可能性に希望を感じます。
「発信する側」ではなく「つなぐ側」として、これからも小さな声や熱量を拾い上げながら、実直にコミュニティと向き合っていきたいと思います。