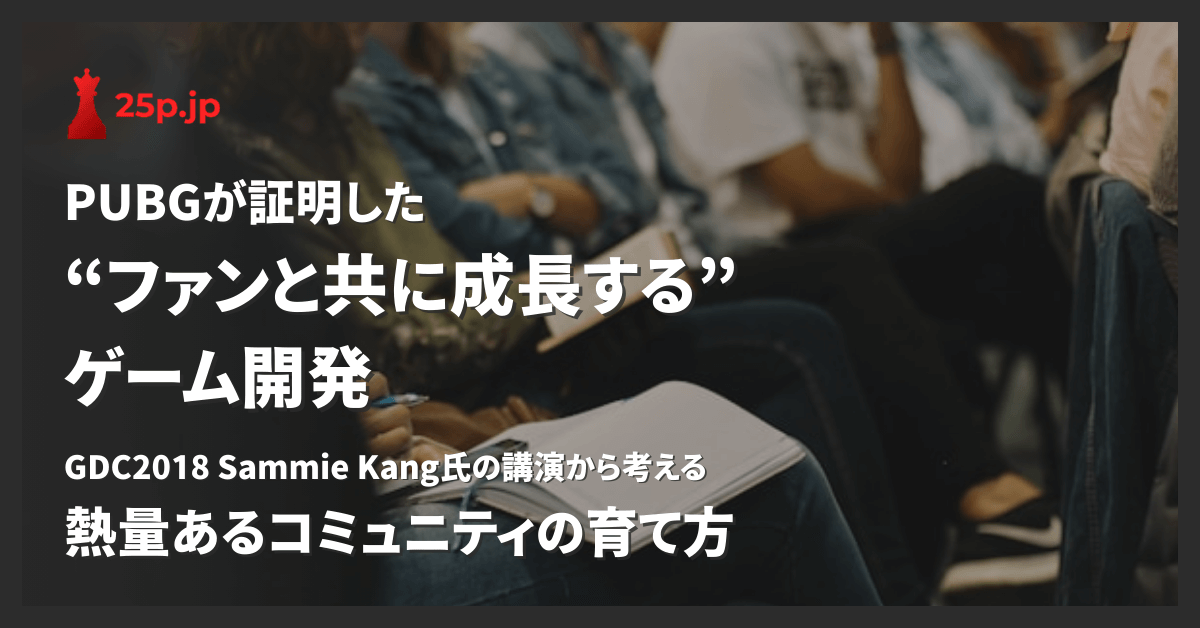この講演では、『PUBG』というタイトルがゼロから世界的なゲームへと成長していく過程、そしてその背景にあったコミュニティ戦略が詳細に語られています。
※本記事は、講演内で語られた具体的なエピソードに触れる箇所もあるため、可能であれば講演をご覧になってから読むことをおすすめします。
この講演を紹介したい背景
私自身、ベータ版の時期からこのゲームに触れ、プレイヤーとしてその急成長を肌で感じてきました。カスタムマッチ機能が登場した頃には、配信者主催のマッチに日常的に参加し、Discordグループを通じて他のプレイヤーと交流するようになりました。その時の熱気や一体感は、今でも鮮明に覚えています。
このような思い入れのあるタイトルだからこそ、「25p.jp」最初のコミュニティカテゴリー記事として、紹介することに意味があると感じました。
執筆の動機:プレイヤー視点と運営者の視点の交差点
この講演を視聴して強く感じたのは、かつてプレイヤーとして体験していたあの熱狂の裏側に、どれほど丁寧な戦略と努力があったかということ。そして、それが現在の仕事に深くつながっているという気づきでした。
私は現在、海外ゲームの日本向けSNS発信を担当しており、コミュニティ運営等も行っています。Sammie氏の講演には、今の業務とリンクするポイントが数多くありました。
インディーでもできる。予算がなくても、コミュニティは育てられる
Sammie氏の言葉で、PRや広告だけに頼らず、ファンと向き合いながら“共に成長する”姿勢がどれだけ強い推進力になるかを再認識しました。
講演から学んだ、熱量あるコミュニティの育て方
1. Community Snowballing(雪だるま式の成長戦略)
少人数の熱量あるファンとの関係性を育てることで、自然と広がりが生まれる
この考え方には強く共感しました。初期の段階で密度の高い関係性を築ければ、それはやがて波紋のように広がっていきます。講演で語られた「Donald Duckが雪玉を転がすように」という比喩も、非常に腑に落ちるものでした。
2. 低予算でもできる、ストリーマーとの信頼構築
トップ配信者に依存しない、双方向の関係性が鍵
中規模や新進気鋭のストリーマーと丁寧に関係を築くことで、限られた予算の中でも大きな効果を生み出せる。これは、現在関わっているプロジェクトでも実感している重要なポイントです。
3. 不完全でも見せる勇気
完成していなくても、開発中の姿を見せて一緒に育てる
講演で語られた「怖かったけど、見せることが仲間として迎え入れる合図だった」という言葉には深く共感しました。開発の透明性が信頼を生み、それが共感や支援につながることを、何度も見てきました。
4. “中の人”の存在を伝える発信
人を感じる発信が、ファンとの距離を縮める
開発者や運営担当の“顔が見える”発信は、ファンとの絆を深める大きな要素です。Sammie氏が「PoopyQueen」という愛称で活動していたエピソードも、人としての温度感を伝える大切さを物語っていました。
プレイヤー体験と講演内容が重なった瞬間
この講演を通じて、かつて感じていた熱狂や感動の裏に、しっかりとした戦略と設計があったことを知り、大きな学びがありました。
当時の私は「PoopyQueen」という存在を知らなかったものの、有名配信者がスキンの交換コードを配っていた様子を今でも覚えています。「あの配信を見れば何かがもらえるかも」といった期待感が、自然な形でコミュニティに浸透していたのです。それが意図された仕掛けであり、かつうまく機能していたという事実に、今回あらためて驚かされました。
総括:熱量あるコミュニティとは何か?
この講演が示した“熱量あるコミュニティの育て方”とは、特別な技術や巨額の資金ではなく、小さな対話の積み重ねと、相手を尊重する姿勢の中にあると感じました。ソーシャルメディアマネージャーやコミュニティマネージャーにとって、こうした積み重ねこそがユーザーとの信頼関係を築く核心であり、日々の運用で最も大切にすべき視点だと思います。
丁寧なやりとりや、相手を“インサイダー”として迎え入れる意識。そして、怖くても見せていく透明性。これらが積み重なっていくことで、結果として大きな共感と広がりが生まれるのだと思います。
PUBGは、私にとってただのゲームではありません。仲間と過ごした時間、競い合った記憶、そして今の仕事の原点でもあります。
ゲームを通じて人が動く。その瞬間に立ち会えた経験は、私にとってかけがえのないものです。
そして、その変化を生み出す力は、いつも特別な誰かだけが持っているわけではなく、小さな行動や丁寧な姿勢の中にあるのだと、改めて実感しました。
これからも、現場で感じた気づきを、私なりの言葉で記録していけたらと思います。